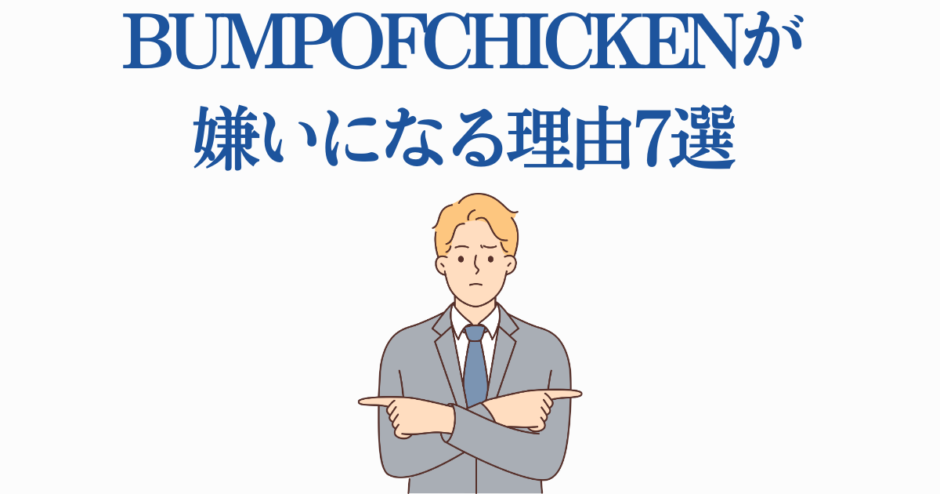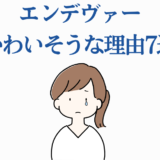本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作しています。
かつて心の支えだったBUMP OF CHICKENの音楽に、いつからか違和感を覚えるようになった──そんな複雑な感情を抱えているファンは少なくありません。「メロディが複雑すぎる」「昔のシンプルさが失われた」「タイアップばかりで商業的になった」という声がSNSにあふれ、2026年2月11日のバンド結成30周年を前に、音楽性の変化に対する評価が二極化しています。本記事では、多くのファンが共通して挙げる「嫌いになった理由7選」を客観的に分析。あなたが感じていた違和感の正体を言語化し、今後のバンドとの付き合い方を考えるヒントを提供します。
BUMP OF CHICKENを嫌いになった人が増えている現状
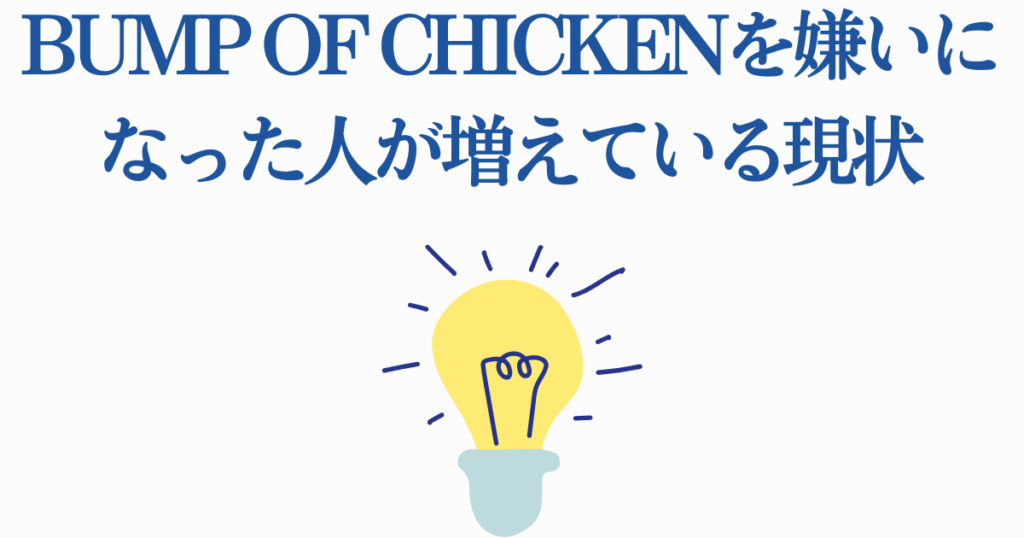
かつて心の支えだったBUMP OF CHICKENの音楽に、いつからか違和感を覚えるようになったというファンが増えています。SNSやブログには「ついていけなくなった」「昔のバンプが好きだった」という声があふれ、長年愛してきたバンドへの複雑な感情を抱えている人たちが少なくありません。2026年2月11日にバンド結成30周年を迎えるBUMP OF CHICKENですが、この節目を前に音楽性の変化に対する評価が二極化しています。
SNSで広がる「ついていけない」という声
TwitterやnoteといったSNSでは、BUMP OF CHICKENの音楽性変化について語るファンの投稿が目立つようになっています。「メロディーが複雑すぎて、昔のようなシンプルな良さが失われた」「調性感のないメロディーが増えて、耳に残らなくなった」という具体的な指摘から、「最近の曲は全然聴いていない」という距離を置く宣言まで、様々な形で戸惑いの声が表明されています。
特に印象的なのは、「嫌いになったわけじゃないけど、結果として聴かなくなった」という表現です。バンドへの愛情は変わらないものの、新作に対して素直に共感できなくなってしまった葛藤が、この言葉には滲んでいます。こうした声は批判というよりも、むしろ自分の感覚が間違っているのではないかという不安や、長年のファンとしての自分を見失いかけている焦りを含んでいるのが特徴的です。
ファン層の世代交代と古参ファンの葛藤
BUMP OF CHICKENのファン層は、バンドの歴史の中で何度も大きく入れ替わってきました。『天体観測』で爆発的な人気を獲得した2000年代初頭、『COSMONAUT』でアリーナバンドへと成長した2012年前後、そして『RAY』以降の電子音を導入した2014年以降と、それぞれの時期に新しいファン層が形成されてきました。
音楽ライターからは「ファン、総入れ替わりしてない?」という指摘も出ており、実際に現在のライブ会場には10代〜20代前半の若いファンが多く見られます。1999〜2010年頃の初期〜中期作品に強い思い入れを持つ古参ファン層にとって、この状況は複雑です。自分たちが愛した「あの頃のBUMP」を知らない世代が主流になりつつあることで、かつての自分の居場所が少しずつ失われていくような寂しさを感じているのかもしれません。
一方で、こうしたファン層の変化はBUMP OF CHICKENの進化の証でもあります。20年以上活動を続ける中で、同じ音楽性を保ち続けることの方が難しいのは事実です。しかし古参ファンにとっては、頭では理解できても心がついていけないというジレンマが生まれています。
30周年を前に顕在化する変化への評価
2026年2月11日のバンド結成30周年を控え、BUMP OF CHICKENの軌跡を振り返る動きが活発化しています。この節目を前にして、これまで漠然と感じていた「何かが違う」という違和感を言語化しようとするファンが増えているのです。30周年という特別な年を迎えるにあたり、自分とバンドの関係性を改めて見つめ直す時期に来ているのかもしれません。
音楽メディアでも、バンドの変遷を特集する記事が増えており、初期のシンプルなロックサウンドから現在の洗練された楽曲群までを俯瞰する機会が増えています。こうした振り返りの中で、「どの時期のBUMPが好きか」という話題は避けて通れないテーマとなっています。
30周年に向けて大規模なツアーや記念アルバムの発売が期待される中、古参ファンの間では「初期の楽曲を演奏してほしい」という声が高まっています。一方で、バンド自身がどのような形で30年の集大成を示すのか、その選択が今後のファンとの関係性を大きく左右することになるでしょう。この重要な節目を前に、「嫌いになった」という感情と向き合うファンたちの葛藤は、より深まっているのが現状です。
BUMP OF CHICKENの音楽性が変わった5つの転換点
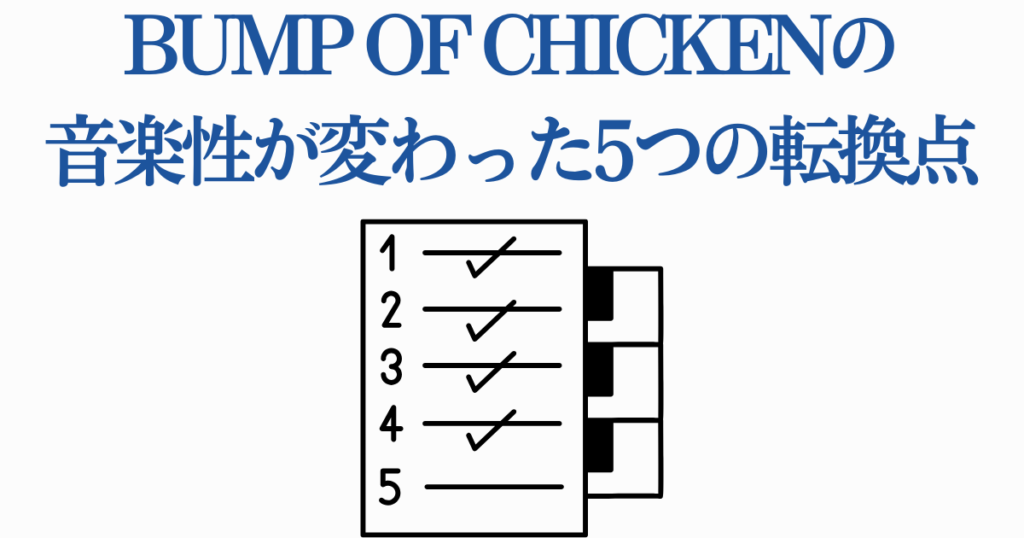
BUMP OF CHICKENの音楽性は、バンド活動の25年以上の歴史の中で着実に進化を遂げてきました。その変化は決して突然訪れたものではなく、いくつかの明確な転換点を経て段階的に進んできたものです。特に2010年代以降の変化は顕著で、初期のシンプルなロックサウンドから、より複雑で洗練された音楽性へとシフトしてきました。ここでは、ファンの間で特に大きな議論を呼んだ5つの転換点を時系列で見ていきます。
2014年『RAY』でのボーカロイド起用と電子音導入
2014年3月にリリースされたアルバム『RAY』は、BUMP OF CHICKENの歴史において最も大きな転換点の一つとなりました。このアルバムで最も話題を呼んだのが、表題曲「ray」における初音ミクとのコラボレーションです。BUMP OF CHICKENとしては初のフィーチャリング・アーティストとの楽曲となり、従来のファンに大きな衝撃を与えました。
「ray」のボーカロイド版は配信限定でリリースされ、わずか3日で100万回再生を突破するなど、新しいファン層の獲得に成功した一方で、古参ファンからは賛否両論の声が上がりました。SF映画のオープニングを思わせる壮大なインストゥルメンタル「WILL」で幕を開けるこのアルバムは、シンセサイザーを効果的に使用したダンサブルな楽曲が特徴的で、「虹を待つ人」ではスペーシーなシンセ音を重ねたアレンジが採用されています。
この時期から、BUMP OF CHICKENの楽曲にはキラキラとしたPOPチューンとしての側面が強まり、従来のギター中心のロックサウンドから、多彩な電子音を取り入れた音楽性へと大きくシフトしました。『RAY』リリース直後の「WILLPOLIS 2014」ツアーでは、東京ドーム公演という新たなステージに立ち、バンドとしての成長を示しましたが、同時に「これはBUMPじゃない」と感じるファンも少なくありませんでした。
2016年『Butterflies』でのEDMサウンドへの接近
『RAY』から約2年後の2016年2月にリリースされたアルバム『Butterflies』では、さらに音楽性の変化が加速しました。このアルバムでは、EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)の要素が前作以上に色濃く反映され、打ち込みを多用したダンサブルなサウンドが特徴となっています。
升秀夫のドラミングは32分音符でハイハットを刻むなど、初期の8ビート中心だった頃と比較すると4倍の速度に進化しており、まるで打ち込み音楽のような精密さを持つようになりました。この演奏技術の向上は、バンドとしての成長を示すものですが、同時に「人間臭さ」や「大味さ」を失ったという意見も出ています。
『Butterflies』のリリース翌日には、バンド結成20周年記念Special Live「20」が千葉・幕張メッセで開催され、2万5000人を動員しました。その後のスタジアムツアーでは全6公演で計28万人を動員し、特に横浜国際総合競技場(日産スタジアム)での2日間公演は14万人を集めるなど、商業的には大成功を収めました。しかし、この圧倒的な人気の背後で、初期の楽曲を愛するファンたちは、自分たちの知っているBUMPとの距離を感じ始めていました。
2010年代からのタイアップ楽曲の急増
BUMP OF CHICKENは元々、タイアップを積極的に行わないスタンスで知られていました。2009年以前は1年に1回タイアップがあれば多い方で、むしろ「ブラウン管の前で評価されたくない」と語るなど、メディア露出を控える姿勢を貫いていました。
しかし2010年以降、この方針は大きく転換します。年間複数のタイアップを手がけるようになり、テレビドラマやアニメの主題歌として楽曲が使用される機会が急増しました。2019年には1年で5つものタイアップを実施し、最新アルバム『Iris』では13曲中10曲がタイアップ曲という状況になっています。
この変化に対して、古参ファンからは「広告代理店からお金をもらって作る曲はロックではない」という厳しい批判も出ています。特に象徴的だったのは、2015年の紅白歌合戦への初出場です。かつて「地デジならいいのかよ」と皮肉を込めて語られたように、テレビ出演を避けてきたバンドがお茶の間に登場したことで、スタンスの変化を決定的に印象づけました。
シンプルなロックサウンドから複雑な楽曲構造への進化
初期のBUMP OF CHICKENの楽曲は、パワーコードを中心としたシンプルなロックサウンドが特徴でした。「天体観測」や「ダンデライオン」のように、誰でも演奏しやすい構成の楽曲が多く、それが「バンドを始めたくなる音楽」としての魅力につながっていました。
しかし2012年の『COSMONAUT』あたりから、楽曲構造は徐々に複雑化していきます。『orbital period』で見せた演奏技術の向上は、より緻密なアレンジを可能にしましたが、同時に初期の持っていた「荒削りな熱量」は薄れていきました。分数コードの多用、変拍子の導入、複雑なギターアルペジオなど、音楽理論に基づいた洗練されたサウンドメイクが特徴となっています。
この進化について、音楽的には明らかに成長しているという評価がある一方で、「家で食べるチャーハンと高級中華料理店の炒飯」に例えられるように、技術的には優れていても心に響かなくなったという声もあります。かつての「脳が退化する」ほどのシンプルな気持ちよさを求めるファンにとって、この複雑化は受け入れがたい変化でした。
メロディラインの複雑化と調性感の変化
BUMP OF CHICKENのメロディは、元々独特の癖があることで知られていました。手癖で入ってくる外れた音が魅力の一つでしたが、近年はその傾向がさらに顕著になり、「調性感のないメロディ」「メロディとコードがしっかりくっついていない」という指摘が増えています。
藤原基央自身は「いいメロディー、いいコード進行、いいリズム」を音楽の最も重要な三要素と語っていますが、最近の楽曲については「『いいメロディー』よりも『作曲上のテク』に走っているのではないか」という疑問の声も上がっています。メロディの複雑性は確かに年々上昇しており、従来のファンの中には「突然何かの閾値を超えてしまった」と感じる人も少なくありません。
特に2020年代の楽曲では、サビのメロディが耳に残りにくくなったという意見が目立ちます。初期の楽曲が持っていた「一度聴いたら忘れられない」キャッチーさが薄れ、何度聴いても覚えられない複雑なメロディラインに変化してきたことが、ファンの離脱を招く一因となっています。この変化は、シンプルな感動を求めるリスナーと、音楽的な挑戦を評価するリスナーとの間に、大きな溝を生み出すことになりました。
BUMP OF CHICKENが嫌いになる理由7選
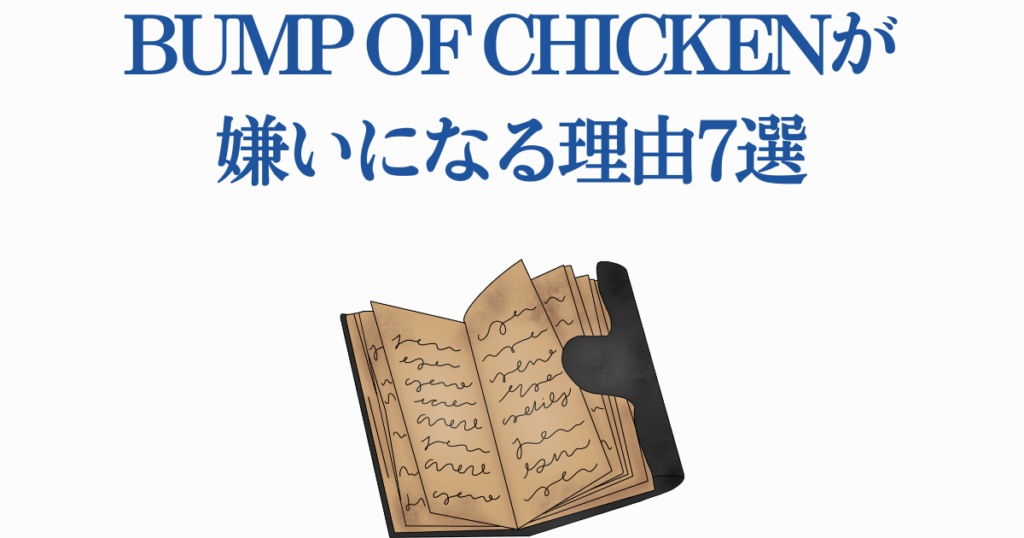
BUMP OF CHICKENを「嫌いになった」と感じるファンたちには、それぞれ明確な理由があります。これらは決して単なる懐古主義や一時的な感情ではなく、バンドの音楽性やスタンスの変化に対する真摯な反応です。ここでは、多くのファンが共通して挙げる7つの理由を詳しく見ていきましょう。自分の感じていた違和感の正体が、ここにあるかもしれません。
嫌いになった理由①メロディの複雑化
BUMP OF CHICKENのメロディが複雑になりすぎて、もはや覚えられないという声が多く聞かれます。初期の楽曲は、一度聴いたら頭の中でずっとリフレインするような、シンプルで強烈なメロディラインが特徴でした。「天体観測」や「K」のような楽曲は、メロディを口ずさみながら日常を過ごせるほど親しみやすいものでした。
しかし近年の楽曲では、メロディが複雑に折れ曲がり、調性感が希薄になっています。あるファンは「メロディーとコードがしっかりくっついていない」と表現し、何度聴いても耳に残らない感覚に戸惑っています。外れた音の使い方が巧妙になった反面、その外れ方が計算されすぎて、かつての「手癖で出てきた偶然の美しさ」が失われてしまったように感じられるのです。
音楽理論に詳しくない一般のリスナーにとって、この変化は特に受け入れがたいものです。なぜなら、メロディの良し悪しを理屈で説明できないまま、ただ「心に響かない」という漠然とした違和感だけが残るからです。クラシックや現代音楽など複雑な音楽を聴いてきたリスナーでさえ「BUMPのメロディについていけなくなった」と語るケースもあり、これは単なる音楽的素養の問題ではないことを示しています。
嫌いになった理由②シンプルさの喪失
初期のBUMP OF CHICKENが持っていた「シンプルさ」は、多くのファンにとってバンドの魅力の核心でした。パワーコードを中心とした直球のロックサウンド、ストレートに心に突き刺さる歌詞、そして何よりも「ギターを手に取りたくなる」衝動を駆り立てる演奏。これらすべてが、余計な装飾を削ぎ落としたシンプルさから生まれていました。
ところが現在の楽曲は、多層的なシンセサイザー、緻密に計算されたアレンジ、高度な演奏技術を要する複雑なフレーズなど、かつてのシンプルさとは対極にある要素で構成されています。音楽的なクオリティは確かに向上していますが、それと引き換えに失われたものも大きいのです。
「脳が退化するほど単純で気持ちいい」と評された初期サウンドを愛したファンにとって、現在の洗練されたサウンドは「高級すぎて日常から遠い」と感じられます。家で食べるチャーハンと高級中華料理店の炒飯、どちらも美味しいけれど求めているのは前者だった、という例えがぴったり当てはまるのです。シンプルさこそがBUMPの本質だと信じていたファンにとって、この変化は受け入れがたいものとなりました。
嫌いになった理由③タイアップ路線
「ブラウン管の前で評価されたくない」と語り、メディア露出を極力避けてきたBUMP OF CHICKENが、2010年代から急速にタイアップ路線へと舵を切ったことは、多くのファンに衝撃を与えました。2009年以前は年に1回程度だったタイアップが、2010年以降は急増し、近年では年間5つものタイアップを手がけることも珍しくありません。
タイアップそのものが悪いわけではありませんが、問題はその頻度と、楽曲制作の姿勢です。広告代理店や制作委員会の要望に応じて作られた楽曲は、たとえどれほど完成度が高くても「ロック」の精神からは遠いと感じるファンがいます。「このドラマ・アニメに合わせた曲を作ってください」という依頼で生まれた音楽に、かつてのBUMPが持っていた「自分たちの表現したいものを表現する」という純粋さを感じられないのです。
2019年リリースの『Iris』は13曲中10曲がタイアップ曲という構成で、もはやオリジナルアルバムというよりタイアップ曲の寄せ集めに見えてしまいます。作品としての一貫性やアルバムコンセプトよりも、個別のタイアップ案件を優先した結果ではないかという疑念が、ファンの心に生まれています。かつて音楽そのもので勝負してきたバンドが、商業主義に飲み込まれていくように見えることが、古参ファンの失望を招いているのです。
嫌いになった理由④スタンスの変化
BUMP OF CHICKENのスタンス変化を象徴する出来事が、2015年の紅白歌合戦初出場です。「ブラウン管の前で評価されたくない」と明言し、テレビ出演をほとんど行ってこなかったバンドが、最もお茶の間向けの音楽番組に登場したことで、多くのファンが「何かが終わった」と感じました。
ファンクラブを持たない、メディア露出を控える、ライブを中心に活動する──こうした姿勢は、BUMP OF CHICKENのアイデンティティそのものでした。「楽曲だけで勝負する」「ファンに序列をつけない」という哲学は、商業音楽業界において異端でありながら、だからこそ多くの支持を集めていたのです。
しかし2010年代以降、この「仙人のような」スタンスは徐々に変化していきます。メディア出演の増加、タイアップの急増、そして何より「売れるための努力」が見え隠れするようになりました。藤原基央の結婚発表(2020年)も、これまでプライベートを一切公表してこなかった姿勢からの転換として注目されました。バンドが人間に戻ろうとしたのだという解釈もありますが、同時にそれは「特別な存在」であることをやめたということでもあります。かつての「丸腰」の強さを失ったように見えることが、一部のファンの離反を招いています。
嫌いになった理由⑤歌詞の方向性
藤原基央の歌詞は、抽象的でありながら心の深い部分に響く独特の世界観で知られていました。初期の楽曲では、青春の葛藤、孤独、希望といった普遍的なテーマを、宇宙や光といったモチーフを通して表現していました。「ガラスのブルース」や「ダイヤモンド」のような楽曲は、具体的な状況を描きながらも、聴く人それぞれが自分の物語を重ねられる余白がありました。
しかし近年の歌詞については、「子供の頃の思い出に取り憑かれたよう」「優しい曲ばかりで抜け殻のよう」という批判が出ています。特に2020年代の楽曲では、「優しさ」や「繋がり」をテーマにしたフワッとした歌詞が増え、かつての切実さや痛みを伴う感情表現が薄れてきたという指摘があります。
朝ドラ主題歌「なないろ」や『すみっコぐらし』主題歌「Small world」のような楽曲は、老若男女に受け入れられる普遍性を持つ反面、「誰にでも当てはまるということは、誰にも刺さらないということでもある」という見方もできます。かつて「汚れたって受け止めろ 世界は自分のモンだ」と叫び、現実に引きずり出すような力強さがあった歌詞が、今では癒し系の優しいメッセージに変わってしまったことに、物足りなさを感じるファンは少なくありません。
嫌いになった理由⑥ファン層の変化
「ファン、総入れ替わりしてない?」という指摘が示すように、BUMP OF CHICKENのファン層は大きく変化しています。現在のライブ会場には、『天体観測』や『カルマ』を知らない10代〜20代前半の若いファンが多く見られ、彼ら彼女らにとってのBUMPは『RAY』以降の音楽性が当たり前なのです。
この世代交代自体は、長く活動するバンドにとって自然なことですが、古参ファンにとっては寂しさを感じる要因となっています。ライブで周りを見渡したとき、初期の楽曲で盛り上がる人が少なくなり、逆に自分が知らない新曲で若いファンたちが熱狂している光景は、「自分の居場所がなくなった」という感覚を生み出します。
さらに、新しいファン層の一部には、古参ファンからすると「痛々しい」と映る行動をとる人もいます。SNSでの過剰な称賛、40代になったメンバーに対する「可愛い」というコメント、他のバンドを見下すような発言など、熱心さゆえの行き過ぎた言動が目につくことがあります。こうした新しいファンコミュニティの雰囲気に馴染めず、距離を置くようになった古参ファンもいるのです。
嫌いになった理由⑦メンバーの不祥事
2020年9月、ベースの直井由文の不倫報道は、BUMP OF CHICKENとファンの関係に大きな亀裂を生みました。結婚していたことを隠して一般女性と交際していたという内容は、相手の女性を深く傷つけるものであり、多くのファンに失望を与えました。直井は活動を一時休止し、2021年6月に復帰しましたが、この出来事がバンドへの信頼を揺るがせたことは事実です。
特に衝撃的だったのは、「楽曲だけで勝負する」「人間性ではなく音楽を見てほしい」というスタンスを貫いてきたバンドで起きた出来事だったからです。プライベートを公表せず、メンバーの人間性よりも楽曲の力を信じてきたファンにとって、その「楽曲の背後にいる人間」の行動が信頼を裏切るものだったことは、大きなジレンマを生み出しました。
「音楽と人格は別」という考え方もありますが、BUMP OF CHICKENの歌詞が持つメッセージ性の強さゆえに、その作り手の行動との矛盾を感じずにはいられないファンもいます。「仲間を大切にする」「誠実であること」といったテーマを歌ってきたバンドのメンバーが、現実では不誠実な行動をとっていたという事実は、楽曲への没入を妨げる要因となりました。この出来事以降、「もう純粋な気持ちで楽曲を聴けなくなった」という声は決して少なくありません。
それでもBUMP OF CHICKENを支持するファンの声

「嫌いになった」という声がある一方で、BUMP OF CHICKENの変化を肯定的に受け止め、現在も熱心に支持し続けるファンも数多く存在します。彼らは音楽性の進化をバンドの成長として評価し、新旧両方の楽曲を楽しむ柔軟な姿勢を持っています。2026年の30周年に向けて、こうした肯定的なファンの視点を知ることは、自分とバンドの今後の付き合い方を考えるヒントになるかもしれません。
進化し続ける姿勢への評価
BUMP OF CHICKENの音楽性変化を支持するファンは、「同じことを繰り返すより、挑戦し続ける姿勢こそがロックだ」と語ります。20年以上同じスタイルを貫くことも一つの選択肢ですが、それでは停滞と飽きが訪れるのも事実です。むしろ、批判を恐れずに新しいサウンドに挑戦し、ボーカロイドとのコラボレーションやEDM要素の導入など、ロックバンドの枠を超えた実験を行う勇気こそ評価すべきだという意見です。
藤原基央は「自分基準でいいメロディー、いいコード進行、いいリズム」を追求し続けていると語っており、その探求心が現在の複雑な楽曲を生み出しています。演奏技術の向上も目覚ましく、初期の頃と比較すれば、バンドとしての完成度は明らかに高まっています。『Butterflies』以降のスタジアムツアーでは28万人を動員し、若い世代に確実にメッセージを届けている事実は、彼らの進化が正しかったことを証明しているとも言えます。
40代になったメンバーが、10代の頃と同じ音楽をやり続けることの方が不自然です。人生経験を重ね、音楽的素養を深めた結果として現在のサウンドがあるのであれば、それは自然な成長の過程だと捉えることもできるのです。
新旧両方の楽曲を楽しむファンの視点
新旧両方の楽曲を愛するファンは、「どちらも違う魅力がある」という柔軟な視点を持っています。初期のシンプルなロックサウンドには、若さゆえの勢いと純粋さがあり、現在の洗練された楽曲には、成熟した音楽性と深い表現力があります。どちらが優れているかではなく、それぞれの時期のBUMPを楽しむことができるという姿勢です。
実際、近年のライブでは初期の楽曲も演奏されており、「天体観測」や「ダンデライオン」といった名曲を今でもライブで聴くことができます。2016年の結成20周年記念ライブでは、「ダイヤモンド」「ベル」「ガラスのブルース」など、初期の名曲が披露され、古参ファンを喜ばせました。新曲から入った若いファンが、こうした初期楽曲に触れることで、よりシンプルなロックサウンドの魅力に気づくきっかけにもなっています。
ある支持派のファンは「新曲を聴いて物足りなさを感じたら、昔のアルバムを聴き返せばいい。BUMPは25年分の音楽資産を持っているのだから、その中から好きな時期の楽曲を選んで聴けばいい」と語ります。バンドの全時期を等しく愛する必要はなく、自分の好きな時期の音楽を大切にしながら、新しい挑戦も見守るという距離感が、長く付き合うコツなのかもしれません。
30周年に向けた期待と希望
2026年2月11日のバンド結成30周年に向けて、多くのファンが期待を寄せています。20周年では幕張メッセで特別ライブが開催され、25周年では「Silver Jubilee」と題したツアーが行われました。30周年という大きな節目では、さらに特別な企画が予想されており、初期楽曲の再演や記念アルバムのリリースを望む声が高まっています。
SNSでは、30周年ライブのセットリスト予想を投稿するファンが増えており、「『ダンデライオン』を聴きたい」「『ギルド』を30周年で演奏してほしい」といった具体的な希望が語られています。こうした予想を楽しむこと自体が、ファンコミュニティの新しい楽しみ方となっており、30周年が単なる記念日ではなく、ファン同士が繋がり、期待を分かち合う機会になっています。
また、30周年を機に、これまで距離を置いていたファンが再びBUMPに向き合うきっかけになる可能性もあります。長い歴史を振り返る特集記事や映像作品が制作されることで、自分が愛した時期のBUMPを再発見し、現在の音楽性との違いを改めて理解する機会になるかもしれません。30周年は、バンドとファンが互いの歩んできた道を振り返り、これからの関係性を再構築するための大切な転換点となるでしょう。
一部のファンは「30周年で何か変わるかもしれない」という希望を持っています。バンドが初心に帰り、シンプルなロックサウンドの楽曲を披露する可能性、あるいは30年の集大成として新旧すべての要素を融合させた新しい作品が生まれる可能性。確かなことは何もありませんが、30年という歴史の重みが、バンドに何らかの特別な決断を促すかもしれないという期待は、多くのファンの心に灯る希望の光となっています。
BUMP OF CHICKENに関するよくある質問

BUMP OF CHICKENの音楽性変化や「嫌いになった」という感情について、多くのファンが共通して抱く疑問があります。ここでは、特に頻繁に検索される5つの質問に答えていきます。
BUMP OF CHICKENはいつから変わったと言われていますか?
BUMP OF CHICKENの音楽性が大きく変わったと言われる最初の転換点は、2012年の『COSMONAUT』です。このアルバムでは演奏技術が飛躍的に向上し、楽曲構造も複雑化しました。当時「バンプは変わってしまった」という声が多く聞かれましたが、決定的な変化は2014年の『RAY』だとされています。
『RAY』では初音ミクとのコラボレーションや電子音の大胆な導入があり、従来のロックサウンドから大きく舵を切りました。さらに2016年の『Butterflies』でEDM要素が強まり、2010年代以降のタイアップ急増も相まって、「もはや別のバンド」と感じるファンが増えていきました。明確な一つの時点ではなく、2012年頃から段階的に変化していったというのが実情です。
初期のBUMP OF CHICKENの魅力は何でしたか?
初期のBUMP OF CHICKENの最大の魅力は、そのシンプルさと力強さの共存にありました。パワーコードを中心としたストレートなロックサウンドは、音楽理論に詳しくない人でも「ギターを手に取りたくなる」衝動を駆り立てるものでした。「天体観測」や「ダンデライオン」のような楽曲は、複雑な技術を要さないながらも、圧倒的なエモーションを持っていたのです。
歌詞も、抽象的でありながら青春期の葛藤や孤独といった普遍的なテーマを扱い、多くのリスナーの心に深く刺さりました。「ガラスのブルース」「K」「ダイヤモンド」といった名曲は、聴く人それぞれが自分の物語を重ねられる余白があり、それが初期BUMPの独特の世界観を形成していました。何より「ブラウン管の前で評価されたくない」という姿勢が、音楽そのもので勝負する純粋さを感じさせ、多くの支持を集めたのです。
BUMP OF CHICKENのファンが総入れ替わりしたって本当ですか?
完全に総入れ替わりしたわけではありませんが、ファン層が大きく変化したのは事実です。現在のライブ会場には、『RAY』以降に ファンになった10代〜20代前半の若い世代が多く見られ、彼らは初期の『FLAME VEIN』や『THE LIVING DEAD』を知らないことも珍しくありません。
音楽ライターからも「ファン、総入れ替わりしてない?」という指摘があり、実際に1999〜2010年頃にファンだった層の一部は、徐々にライブに足を運ばなくなっています。一方で、古参ファンの中にも新旧両方を楽しむ層は確実に存在し、30年近い活動の中で複数のファン層が併存している状態です。世代交代が進んでいることは確かですが、「総入れ替わり」というより「多層化」と表現する方が正確かもしれません。
30周年でBUMP OF CHICKENは昔の曲をやりますか?
2026年2月11日の30周年記念イベントでは、初期楽曲の演奏が期待されています。過去の周年記念ライブを見ると、20周年の「Special Live 20」では「ベル」「ダイヤモンド」「ガラスのブルース」など初期〜中期の名曲が披露され、25周年の「Silver Jubilee」でも幅広い年代の楽曲が演奏されました。
30周年という大きな節目では、バンドの歴史を総括する意味でも、初期のシンプルなロックサウンドの楽曲が演奏される可能性は高いでしょう。ファンの間では「30」という数字にちなんだ楽曲選定の予想も盛んで、30曲目の楽曲や「R.I.P.」(メンバーが30歳の時にリリース)などのセットリスト入りを期待する声があります。確実なことは言えませんが、古参ファンの期待に応える演出がなされる可能性は十分にあります。
BUMP OF CHICKENが嫌いになっても罪悪感を感じる必要はありますか?
罪悪感を感じる必要は全くありません。音楽の好みは変化するものですし、バンドの音楽性が変われば、それについていけなくなることは自然なことです。長年愛してきたバンドだからこそ、「嫌いになった」と感じることに罪悪感を抱く気持ちは理解できますが、それはあなた自身の感覚を否定することにつながります。
大切なのは、自分の音楽的嗜好に正直になることです。新しい音楽性を受け入れられないなら、初期〜中期の楽曲だけを聴き続ければいいですし、完全に距離を置くという選択肢もあります。逆に、しばらく離れてから再び聴いてみると、違った印象を受けるかもしれません。「ファンであり続けなければならない」という義務はありません。
また、「嫌いになった」という感情は、それだけ深く愛していた証拠でもあります。どうでもいいバンドなら、変化しても何も感じないはずです。その感情を大切にしながら、自分にとって心地よい音楽との付き合い方を見つけることが、何より重要なのです。
BUMP OF CHICKENが嫌いになる理由7選まとめ

BUMP OF CHICKENを「嫌いになった」と感じるファンたちの声は、決して一時的な感情や単なる懐古主義ではありません。メロディの複雑化、シンプルさの喪失、タイアップ路線への転換、スタンスの変化、歌詞の方向性の変化、ファン層の世代交代、そしてメンバーの不祥事という7つの理由は、それぞれがバンドの音楽性や姿勢の変化に対する真摯な反応です。
長年BUMP OF CHICKENを愛してきたからこそ感じる違和感、かつて心の支えだった音楽に共感できなくなった悲しさ、そして「自分の感覚がおかしいのではないか」という不安──これらすべてが、あなた一人だけの感情ではないことを、この記事を通じて理解していただけたのではないでしょうか。
音楽は時代とともに変化し、バンドも成長します。2014年の『RAY』から2016年の『Butterflies』を経て、BUMP OF CHICKENは確実に新しいステージへと進みました。その進化を肯定的に捉え、新しい音楽性を楽しむファンがいる一方で、初期のシンプルなロックサウンドを愛し続けるファンもいます。どちらが正しいということはなく、それぞれの付き合い方があっていいのです。
今、あなたに残された選択肢はいくつかあります。新しい音楽性を受け入れる努力をしてみる、初期〜中期の楽曲だけを聴き続ける、完全に距離を置く、あるいは2026年の30周年という節目まで様子を見る──どの選択も正しく、どの選択も間違っていません。
2026年2月11日、BUMP OF CHICKENは結成30周年という大きな節目を迎えます。この特別な日に向けて、バンドがどのような姿を見せてくれるのか、初期の楽曲を演奏してくれるのか、それとも新しい挑戦を示すのか。30年の歴史を振り返ることは、あなた自身とバンドの関係を見つめ直す機会にもなるはずです。
「嫌いになった」という感情に罪悪感を感じる必要はありません。それだけ深く愛していた証拠です。その感情を大切にしながら、自分にとって心地よい音楽との付き合い方を見つけてください。BUMP OF CHICKENという存在が、あなたの人生の一時期に寄り添ってくれた事実は、何も変わらないのですから。
 ゼンシーア
ゼンシーア