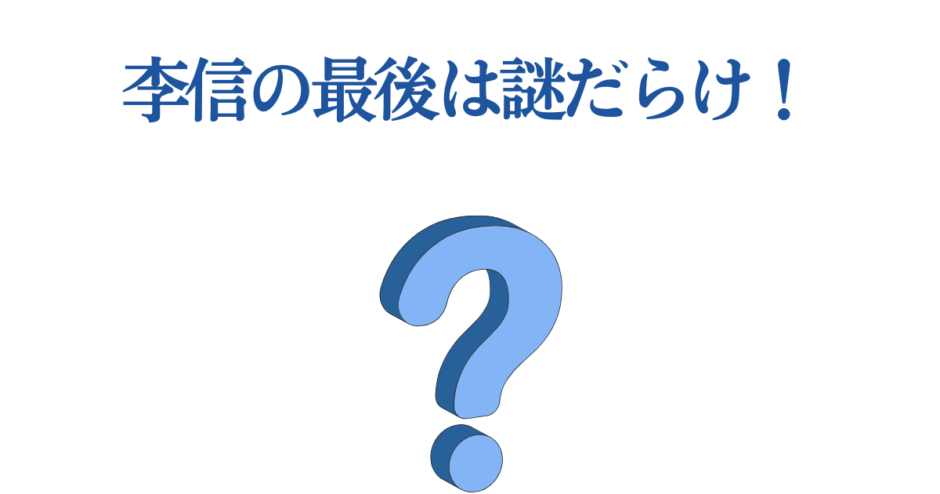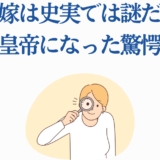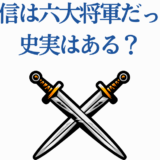本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
中華統一という歴史的偉業を成し遂げた秦の若き将軍・李信。燕の太子丹を討ち取り、斉を滅ぼして天下統一を完成させた英雄でありながら、その最後は歴史の謎に包まれている。紀元前221年を最後に史書から忽然と姿を消し、秦滅亡時の動乱にも一切関与していない不可解な記録の断絶。一体なぜ、これほど重要な人物の足跡が途絶えてしまったのか。
キングダムファンなら誰もが気になる「信の最後」について、史実の謎を徹底検証し、漫画での結末予想まで深掘りする。趙高の大粛清説、帰農隠退説、そして羌瘣との運命的な結婚まで、李信を巡る全ての謎に迫っていこう。
李信の最後の活躍と史実での記録消失
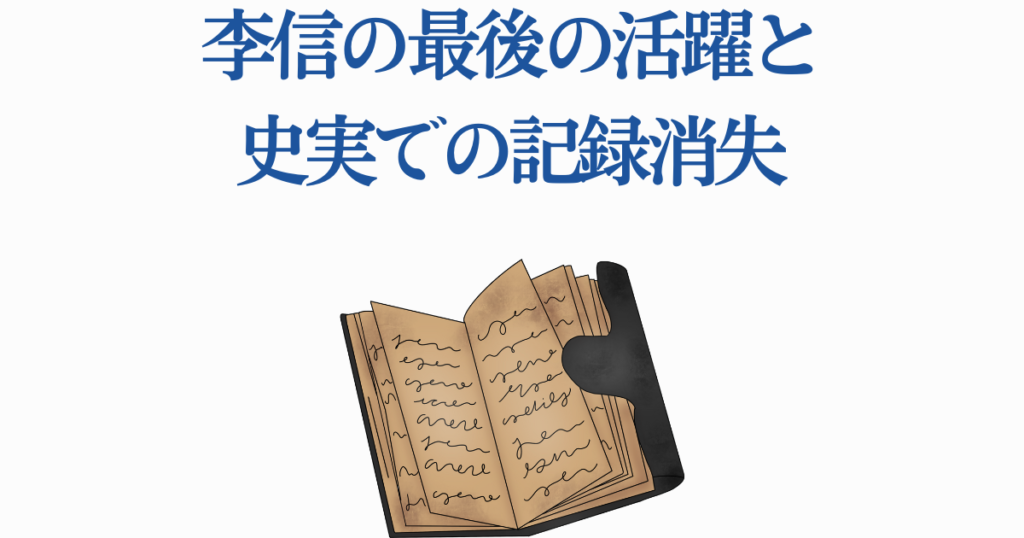
中華統一を目前にした戦国時代末期、秦王政(後の始皇帝)の右腕として活躍した李信。しかし史書を紐解くと、天下統一を果たした紀元前221年を最後に、この若き将軍の記録は忽然と姿を消してしまう。まるで歴史の闇に飲み込まれたかのように、その後の動向は一切不明となっているのだ。
李信の史実における最後の記録を辿ると、そこには三つの重要な局面が浮かび上がってくる。燕の太子丹討伐での大活躍、楚攻めでの屈辱的大敗とその後の復活、そして中華統一の最後を飾る斉滅亡戦への参加である。これらの戦いを通じて、李信は秦王政から絶大な信頼を勝ち取った一方で、史上稀に見る大敗北も経験している。
興味深いことに、楚攻めでの大敗後も李信が粛清されなかったという事実は、当時の秦の厳格な軍法を考えると極めて異例だった。通常であれば戦敗将は処刑されるか、最低でも降格処分を受けるのが常識であったにも関わらず、李信は何事もなかったかのように戦場に復帰している。この謎めいた待遇が、後の歴史家たちに様々な憶測を呼ぶことになった。
太子丹討伐で始皇帝から絶大な信頼を獲得
紀元前227年、燕の太子丹による荊軻の刺客派遣事件は、秦王政を激怒させた。この暗殺未遂事件の報復として、秦は翌年に大軍を派遣して燕の都薊を攻撃し、燕王喜と太子丹を遼東へと敗走させることに成功する。
この燕攻めにおいて、李信は特筆すべき活躍を見せた。わずか千騎ほどの軍勢を率いて敗走する燕軍を執拗に追撃し、ついに衍水まで追い詰めて太子丹を捕らえたのである。この功績は秦王政に強烈な印象を与え、李信の名は一躍諸侯に知れ渡ることとなった。
太子丹討伐の成功により、李信は「智勇兼備」の将軍として秦王政から高く評価されるようになる。史記によれば、この時の李信は「年少で血気の勇があった」と記録されており、若さと勇猛さを兼ね備えた将軍として期待されていたことが分かる。実際、燕の太子丹の口から李信の名前が出るほど、この時期には既に各国に名を轟かせる存在となっていた。
この太子丹討伐が、後の李信の運命を大きく左右することになる。なぜなら、この功績こそが秦王政の李信に対する絶大な信頼の基礎となり、後の楚攻めで大失敗を犯した際も粛清を免れる要因となったからである。
楚攻めでの大敗北とその後の復活劇
紀元前225年、秦王政は長年の宿敵である楚の征服を決意する。この時、楚攻めに必要な兵力について諸将に諮問を行った際、歴戦の名将王翦が「60万の兵が必要」と答えたのに対し、李信は自信満々に「20万で十分」と豪語した。
若き将軍の野心的な発言に心を動かされた秦王政は、王翦を「耄碌した」と評し、李信と蒙恬に20万の大軍を託して楚攻めを命じる。この決断が、李信にとって人生最大の試練となることを、この時誰が予想できただろうか。
戦いの序盤、李信は平輿で、蒙恬は寝丘でそれぞれ楚軍に大勝を収めた。さらに李信は楚の旧都鄢郢を攻撃してこれを破るなど、当初の予想通り快進撃を続けていた。しかし、城父で蒙恬と合流した李信軍を待っていたのは、楚の名将項燕による巧妙な罠だった。
項燕は三日三晩の不眠不休の強行軍で李信軍を追跡し、油断していた秦軍に奇襲攻撃を仕掛けた。この戦いで李信軍は壊滅的な打撃を受け、2か所の拠点を破られ、都尉7名を失うという大敗北を喫することになる。これは秦の統一戦争において、最も屈辱的な敗北の一つとして記録されている。
通常であれば、このような大敗は将軍の処刑を意味した。実際、秦王政は激怒し、隠退していた王翦の元を自ら訪れて謝罪し、再び軍を率いてくれるよう懇願している。しかし驚くべきことに、李信は粛清されることなく、わずか3年後には王賁と共に燕攻略に参加しているのである。この異例の処遇は、李信の太子丹討伐での功績と、秦王政からの深い信頼があったからこそ実現したものと考えられている。
斉滅亡で中華統一を完成させた最後の戦い
楚攻めでの大失敗から見事に復活を果たした李信にとって、最後の大舞台となったのが斉滅亡戦である。紀元前221年、戦国七雄最後の一国となった斉を滅ぼすため、秦は王賁、蒙恬、そして李信の三将軍による連合軍を派遣した。
斉は他国の滅亡を傍観し続け、秦からの賄賂を受け取った家臣の進言により軍備増強を怠っていた。そのため、いざ秦軍が侵攻してきた時には、もはや抵抗する力は残されていなかった。この戦いで李信は、楚攻めでの汚名を完全に雪ぐ活躍を見せ、中華統一という歴史的偉業の完成に大きく貢献することになる。
斉滅亡により、500年以上続いた戦国時代はついに終焉を迎えた。この瞬間、李信は中華統一を成し遂げた将軍の一人として、歴史にその名を刻むことになったのである。しかし皮肉にも、この栄光の瞬間が、史書に記録された李信の最後の姿となってしまった。
興味深いことに、同時代の将軍たちと比較すると、李信の記録の少なさは際立っている。王翦や王賁は『史記』に個別の列伝があり、蒙恬も統一後の活躍が詳細に記録されているのに対し、李信については散発的な記述しか残されていない。この事実が、李信の「最後」を巡る謎をより一層深いものにしているのである。
李信の最後の記録が途絶えた3つの謎
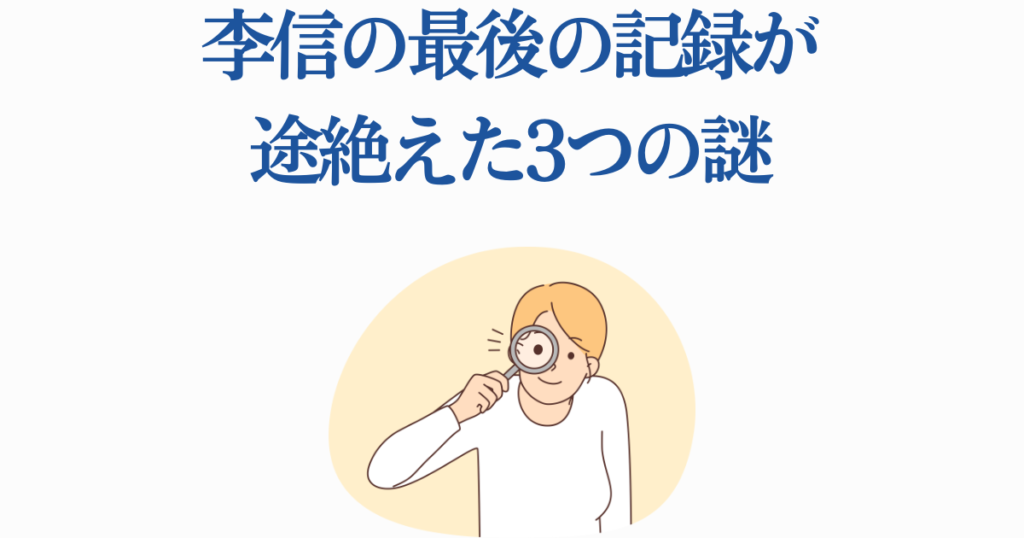
李信の史実を追っていくと、斉滅亡を最後に突然記録が途絶えるという不可解な現象に直面する。中華統一という歴史的偉業を成し遂げた英雄の一人でありながら、なぜその後の動向が一切記録されていないのだろうか。この謎は現代の歴史研究者たちを悩ませ続けており、様々な仮説が提唱されている。
特に興味深いのは、同時代の他の将軍たちとの対比である。王翦や王賁については『史記』に詳細な列伝があり、蒙恬は統一後も万里の長城建設や匈奴討伐で活躍した記録が残されている。にもかかわらず、李信だけが歴史の舞台から忽然と姿を消してしまうのは、一体何を意味するのだろうか。
紀元前221年を最後に史書から完全に姿を消す
紀元前221年、斉を滅ぼして中華統一を完成させた記録を最後に、李信の名前は史書から完全に消失してしまう。この事実は、歴史学者にとって極めて異例かつ不可解な現象として受け止められている。
通常、これほど重要な役割を果たした将軍であれば、統一後の政治や軍事活動についても何らかの記録が残されるのが自然である。実際、同時代の王翦は統一後も政治的影響力を保持し、蒙恬は北方の防衛と万里の長城建設という重要な任務を与えられていた。
ところが李信については、統一後の動向を示す記録が一切存在しない。これは単なる記録の散逸では説明できないレベルの完全な消失である。『史記』の編纂者である司馬遷が、意図的に李信の統一後の活動を記録しなかった可能性も考えられるが、その理由は不明のままである。
より深刻な問題は、李信が消えた後の秦の軍事体制である。統一後の秦では、南方への遠征や匈奴との戦いなど、軍事活動が継続されていた。これらの戦いに、中華統一の立役者の一人である李信が全く関与していないのは、極めて不自然と言わざるを得ない。
この記録の断絶は、李信に何らかの重大な変化が起こったことを示唆している。それが死亡なのか、失脚なのか、あるいは自発的な隠退なのかは、現存する史料からは判断することができない。
秦滅亡時の動乱に李信の名前が一切登場しない
始皇帝の死後、秦は急速に混乱の時代に突入する。紀元前210年の始皇帝崩御から紀元前206年の秦滅亡まで、わずか4年間で巨大帝国は内部から崩壊していった。この激動の時代において、李信の名前が一度も史書に登場しないことは、極めて異常な現象である。
秦末期の動乱では、陳勝・呉広の乱を皮切りに各地で反乱が勃発し、秦軍は章邯や王離(王翦の孫)といった将軍が指揮を執って応戦していた。これらの将軍たちは、李信と同世代か、あるいはより若い世代の人物である。統一戦争で活躍した李信が、この国家存亡の危機に何の役割も果たしていないのは理解し難い。
特に注目すべきは、李信の軍事的能力が高く評価されていたという事実である。楚攻めでの大敗はあったものの、太子丹討伐や斉滅亡での功績は揺るぎないものだった。このような有能な将軍を、秦の指導部が動乱期に活用しないはずがない。
考えられる可能性の一つは、李信がこの時点で既に死亡していたということである。しかし、もし病死や事故死であったならば、それなりの記録が残されるはずである。始皇帝時代の功臣であれば、その死は国家的な出来事として記録されるのが通例だからである。
もう一つの可能性は、李信が政治的な理由で失脚していたということである。趙高の大粛清や政治的混乱の中で、李信が何らかの理由で排除されていた可能性も否定できない。
趙高の大粛清から逃れた可能性と帰農説
始皇帝の死後、宦官の趙高が権力を握ると、秦の政治は一変した。趙高は自らの権力基盤を固めるため、始皇帝時代の重臣や将軍たちを次々と粛清していく。この大粛清の嵐の中で、李信がどのような運命を辿ったかは、彼の最後を考える上で重要な鍵となる。
趙高の粛清リストには、蒙恬や蒙毅といった名将も含まれていた。蒙恬は扶蘇と共に自決を命じられ、蒙毅も処刑された。李斯も趙高の陰謀により腰斬という残酷な刑で処刑されている。これらの事実を考えると、李信も趙高の標的になっていた可能性は十分にある。
しかし興味深いことに、李信が粛清されたという明確な記録は存在しない。もし李信が処刑されていたならば、蒙恬や李斯の場合と同様に、その記録が残されているはずである。この事実は、李信が別の運命を辿った可能性を示唆している。
一つの仮説として、李信が早期に政治の世界から身を引き、帰農したという説がある。楚攻めでの大敗を経験した李信が、政治的な嗅覚を働かせて趙高の権力掌握を予見し、自発的に故郷に隠退した可能性は否定できない。
李信の出身地である槐里は、咸陽から約30キロ離れた農村地帯である。もし李信が早期に故郷に戻り、一般人として生活していたならば、史書に記録が残らないことも説明できる。また、このような「賢明な隠退」は、中国の知識人にとって理想的な生き方の一つとして評価されていた。
さらに、李信の子孫が後の時代まで続いていることも、この説を支持する根拠となる。趙高の粛清を受けた一族は通常、根絶やしにされるか、奴隷身分に落とされるのが常であった。李信の子孫が漢の時代に高官として活躍していることは、李信一族が秦末期の動乱を無事に乗り切ったことを示している。
キングダムでの信の最後はどう描かれる?
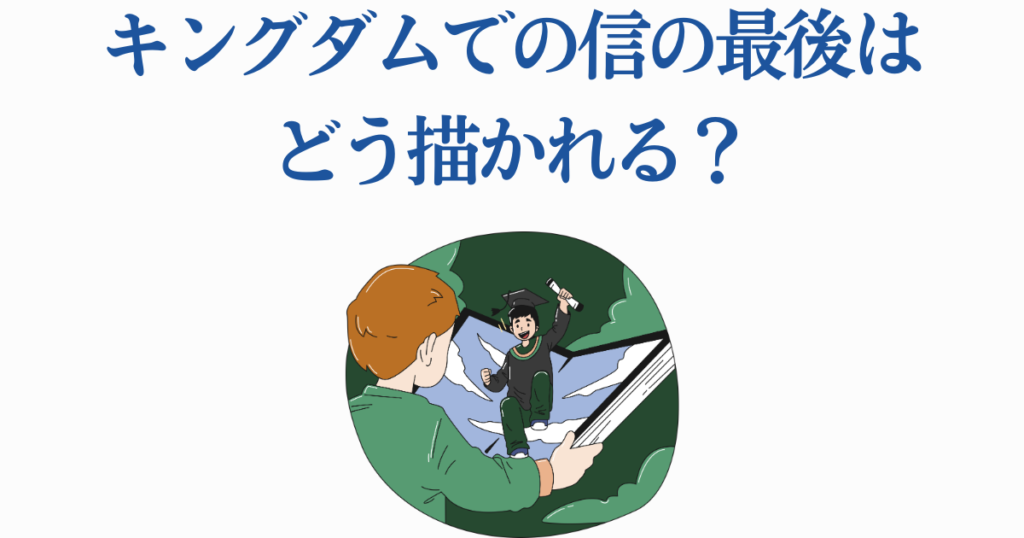
史実では謎に包まれた李信の最後だが、漫画『キングダム』ではどのような結末が待ち受けているのだろうか。原作者の原泰久氏は、これまでのインタビューで「中華統一後もエピローグ的に描く」と明言している。このことから、信の物語は中華統一で終わるのではなく、その後の人生まで描かれる可能性が高い。
キングダムは史実をベースにしながらも、作者独自の解釈や創作要素が多分に含まれた作品である。特に信の生い立ちや人間関係は、史実にはない完全オリジナルの設定となっている。そのため、信の最後についても、史実の制約を受けることなく、作者の描きたい理想的な結末が用意される可能性が高い。
現在のキングダムの展開を見ると、信は着実に「天下の大将軍」への道を歩んでいる。将軍に昇格し、羌瘣とのロマンスも進展し、仲間たちとの絆も深まっている。これらの要素を考慮すると、物語の結末はハッピーエンドに向かう可能性が高いと予想される。
特に注目すべきは、70巻で描かれた信から羌瘣へのプロポーズである。このエピソードは、物語が恋愛要素も含めた総合的な人間ドラマとして完結に向かっていることを示している。
原作者が明かした統一後のエピローグ構想
原泰久氏は複数のインタビューで、キングダムの構想について興味深い発言を残している。特に印象的なのは「中華統一後もエピローグ的に描く」という言葉である。これは、物語が秦による天下統一で終わるのではなく、その後の平和な時代についても描かれることを意味している。
エピローグで描かれる可能性が高いのは、信が「天下の大将軍」として認められる場面だろう。中華統一という偉業を成し遂げた後、論功行賞の場で信が正式に大将軍の地位を与えられるシーンは、物語のクライマックスとして非常に相応しい。このとき、王騎将軍から受け継いだ矛を手に、堂々と立つ信の姿が描かれるかもしれない。
また、平和になった中華で、信が故郷の村を訪れるシーンも考えられる。下僕出身の少年が、ついに頂点まで登り詰めたという感動的な場面として、読者の心に深く刻まれることだろう。この時、漂の墓前で二人の夢が叶ったことを報告する場面が描かれる可能性も高い。
さらに、エピローグでは信の家族についても触れられるかもしれない。史実の李信には子孫が存在するため、キングダムでも信が父親として子どもたちを育てる姿が描かれる可能性がある。特に、飛将軍として名を馳せることになる李広につながる血筋として、信の子どもたちの将来への期待も込められるだろう。
平和な時代における信の姿を描くことで、戦いに明け暮れた青春から、穏やかな大人へと成長した主人公の変化も表現される。これまで戦場でしか輝けなかった信が、平時でも人々を導くリーダーとして活躍する姿は、キングダムという物語の完成形と言えるだろう。
羌瘣か河了貂か運命の結婚相手
キングダムにおける信の恋愛関係は、長らくファンの間で熱い議論の的となってきた。主要な候補として挙げられるのは、飛信隊副長の羌瘣と軍師の河了貂である。この恋愛要素は、単なるロマンスを超えて、信の人間的成長を表現する重要な要素として機能している。
70巻第768話で、ついに信が羌瘣にプロポーズするという衝撃的な展開が描かれた。「この中華統一の戦争が終わったら俺と結婚してくれないか」という信の言葉は、多くの読者に感動を与えた。羌瘣は即答を避けたものの、「嫌じゃない」と答えており、二人の関係が新たな段階に入ったことは明らかである。
このプロポーズが実現した背景には、桓騎将軍の死という衝撃的な出来事があった。不死身だと思われていた桓騎の死を目の当たりにし、信は「生きているうちに伝えるべきことは伝えておこう」という思いに至ったのである。この心境の変化は、信が戦士から一人の男性へと成長したことを示している。
一方、河了貂については、信自身が「妹みたいなもの」と明言していることから、恋愛対象としては見ていない可能性が高い。しかし、河了貂の側には信への特別な感情があることが、作中の随所で示唆されている。特に、凱孟に捕らわれた際の「オレもあいつと一緒に幸せになりたい」という発言は、彼女の心情を如実に表している。
史実を考慮すると、李信には確実に子孫が存在するため、信が結婚して家庭を築くことは確実である。現在の物語の流れから判断すると、羌瘣が結婚相手になる可能性が最も高い。ただし、当時の貴族社会では複数の妻を持つことが一般的だったため、河了貂との関係も何らかの形で決着がつけられるかもしれない。
羌瘣との結婚が実現した場合、二人の間に生まれる子どもが、後に飛将軍として名を馳せる李広につながる血筋となる。この設定により、キングダムの物語は歴史の大きな流れの中に位置づけられ、読者に壮大なロマンを感じさせることになるだろう。
漂の墓参りで物語が完結する感動の結末
キングダムの物語は、信と漂という二人の少年の夢から始まった。「天下の大将軍になる」という共通の目標を抱いて日々鍛錬に励んでいた二人だったが、漂は物語の序盤で命を落としてしまう。しかし、漂の死は決して無駄ではなく、信を政との出会いへと導く重要な役割を果たした。
物語の完結において、最も感動的で象徴的なシーンとなるのは、信が漂の墓前で夢の実現を報告する場面だろう。ついに「天下の大将軍」となった信が、親友の墓前で「やったぞ、漂」と語りかける姿は、読者の涙を誘わずにはいられない。
この墓参りのシーンでは、信一人だけでなく、羌瘣や河了貂、さらには政も同行する可能性が高い。漂の死がきっかけで結ばれた仲間たちが、全員で漂に感謝を捧げる場面は、キングダムという物語の集大成として非常に相応しい。
特に政にとって、漂は自分の影武者として命を犠牲にしてくれた恩人である。始皇帝として中華を統一した政が、一介の下僕だった漂に最大の敬意を表する場面は、身分や出自を超えた人間同士の絆を描くキングダムらしい名シーンとなるだろう。
また、この墓参りのシーンでは、信の成長の軌跡も振り返られるかもしれない。下僕出身の少年が、数々の困難を乗り越えて頂点に立つまでの道のりが、漂への報告という形で語られることで、読者は改めて信の偉大さを実感することになる。
墓前で語られる言葉は、きっとシンプルなものになるだろう。「俺たちの夢、叶えたぞ」「一緒に頂上まで来れなくて悪かった」「でも、お前がいなかったらここまで来れなかった」。そんな素朴な言葉が、読者の心に深く響くはずである。
この漂の墓参りで物語が締めくくられることで、キングダムは単なる戦争漫画ではなく、友情と夢と成長の物語として完結する。読者は涙を流しながらも、満足感に満たされた気持ちで最終ページを閉じることになるだろう。そして、信と漂の友情が、いつまでも心の中に残り続けるのである。
李信の最後に関するよくある質問
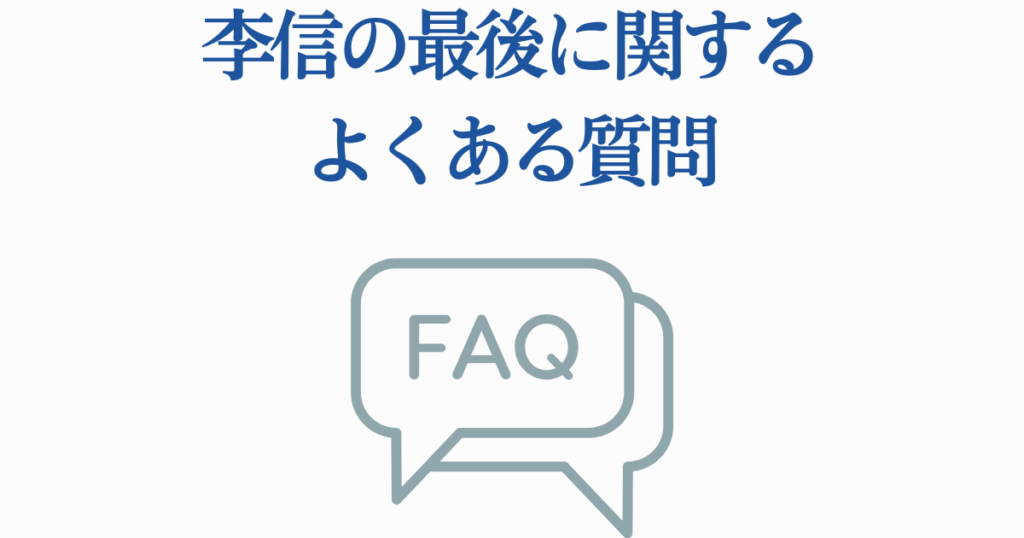
李信の最後について調べている読者から、特によく寄せられる疑問がある。史実の謎めいた記録、秦末期の混乱状況、そしてキングダムでの描き方について、多くの人が同じような疑問を抱いているのだ。ここでは、そうした代表的な質問に対して、現在分かっている情報を基に可能な限り詳しく答えていこう。
これらの質問への回答を通じて、李信という人物をより深く理解し、史実とフィクションの境界線についても考察を深めることができるはずである。また、歴史の謎を探る楽しさと、創作物としてのキングダムの魅力についても、改めて認識できるだろう。
李信は本当に始皇帝より先に死んだのか?
この質問は、李信の最後を考える上で最も重要な疑問の一つである。結論から言えば、李信が始皇帝(紀元前210年崩御)より先に死んだかどうかは、史料不足のため確定的なことは言えない。
ただし、状況証拠から推測すると、李信が始皇帝より先に亡くなった可能性は高いと考えられる。最大の根拠は、始皇帝の死後に起こった秦末期の動乱に、李信の名前が一切登場しないことである。
紀元前209年に陳勝・呉広の乱が勃発し、続いて項羽や劉邦といった英雄たちが次々と挙兵した。この国家存亡の危機において、秦軍を指揮したのは章邯や王離(王翦の孫)といった将軍たちだった。もし李信が生きていたなら、これほどの国難に際して何の役割も果たさないはずがない。
李信は統一戦争において重要な役割を果たした将軍であり、その軍事的能力は広く認められていた。楚攻めでの大敗はあったものの、太子丹討伐や斉滅亡での功績は確かなものだった。このような有能な将軍が、秦の滅亡危機に全く関与していないのは、既に死亡していたと考えるのが最も合理的である。
また、同世代の将軍たちの動向を見ても、王翦や王賁は統一直後に死去したとされ、蒙恬は始皇帝の死後に自殺を命じられている。李信もこれらの将軍と似たような時期に世を去った可能性が高い。
一方で、李信が南方遠征や匈奴討伐などの軍事作戦で戦死した可能性も考えられる。統一後の秦は積極的な対外遠征を行っており、その過程で命を落とした可能性は否定できない。ただし、そのような重要な将軍の戦死が記録に残らないのは不自然であり、この説には疑問も残る。
なぜ秦末期の動乱に李信の名前がないのか?
秦末期の動乱期に李信の名前が全く登場しないのは、確かに謎めいた現象である。この疑問に対する答えとして、いくつかの可能性を検討してみよう。
最も可能性が高いのは、前述したように李信が既に死亡していたという説である。統一戦争の激闘や統一後の遠征で命を落とし、秦末期には既にこの世にいなかったと考えれば、名前が登場しないことも説明がつく。
二つ目の可能性は、李信が政治的な理由で失脚していたという説である。趙高の大粛清や宮廷内の権力闘争に巻き込まれ、公的な地位を失っていた可能性がある。この場合、李信は生きていても軍事的な役割を果たすことができず、結果として歴史の表舞台から消えてしまったということになる。
三つ目の可能性は、李信が早期に引退して故郷に隠居していたという説である。楚攻めでの大敗を経験した李信が、政治的な危険を察知して自発的に公職から身を引いた可能性も考えられる。この「賢明な隠退」は、中国の伝統的な処世術の一つでもある。
また、記録の散逸という要因も考慮する必要がある。秦末期は極度の混乱状態にあり、多くの公的記録が失われた可能性が高い。李信が何らかの役割を果たしていても、その記録が後世に伝わらなかった可能性もある。
さらに、李信の活動が地方に限定されていた可能性も考えられる。中央の政治から距離を置き、地方の防衛や統治に従事していたとすれば、中央政府の記録には残りにくい。特に、故郷の関中地方の防衛に当たっていた場合、その活動は目立たないものだったかもしれない。
興味深いのは、李信の子孫が後の時代まで続いていることである。これは、李信一族が秦末期の動乱を何らかの形で乗り切ったことを示している。趙高の粛清を受けた一族は通常、根絶やしにされるか奴隷身分に落とされるため、李信一族の存続は彼らが政治的な危険を回避できたことを示唆している。
キングダムの信は史実通りの最後を迎えるのか?
キングダムの信が史実通りの最後を迎えるかどうかは、原作者の原泰久氏の構想次第であり、現時点では明確な答えは出せない。ただし、これまでの作品傾向や作者の発言から、いくつかの推測は可能である。
まず重要なのは、キングダムが史実をベースにしながらも、大胆な創作要素を含む作品だということである。信の出自、人間関係、成長過程などは、史実にはない完全オリジナルの設定となっている。このことから、信の最後についても、史実の制約に縛られることなく、作者独自の解釈が示される可能性が高い。
原泰久氏は「中華統一後もエピローグ的に描く」と明言している。これは、物語が統一で終わるのではなく、その後の信の人生も描かれることを意味している。史実の李信は統一後に記録が途絶えるが、キングダムでは統一後の信の活躍や私生活まで描かれる可能性がある。
特に注目すべきは、信と羌瘣の恋愛関係の進展である。70巻でのプロポーズシーンは、物語がハッピーエンドに向かっていることを強く示唆している。史実の李信には確実に子孫が存在するため、キングダムでも信が結婚して家庭を築く姿が描かれる可能性が高い。
また、キングダムは基本的に前向きで希望に満ちた作品である。主人公の信が悲劇的な最後を迎えるよりも、夢を実現して幸せな人生を送る姿が描かれる方が、作品の性格に合っている。読者も、長年応援してきた信に幸せになってほしいと願っているはずである。
一方で、史実の制約も完全に無視することはできない。李信の記録が途絶えるという史実を踏まえ、何らかの形でその説明がなされる可能性もある。例えば、信が自発的に軍務から退いて平和な生活を送るという設定にすれば、史実との整合性も保てる。
最も可能性が高いシナリオは、信が「天下の大将軍」として認められた後、羌瘣と結婚して幸せな家庭を築き、平和な時代を迎えた中華で穏やかな余生を送るというものである。このエンディングは、読者の期待にも応え、史実との矛盾も避けることができる理想的な結末と言えるだろう。
物語の完結において、漂の墓前で夢の実現を報告するシーンが描かれれば、キングダムという壮大な物語にふさわしい感動的な締めくくりとなるはずである。
李信の最後は謎だらけまとめ
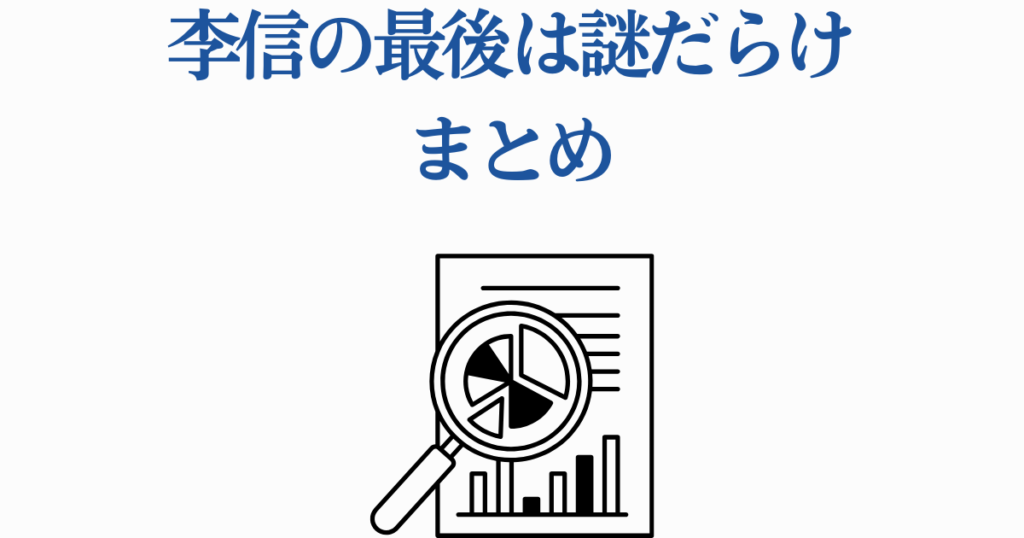
李信の最後について詳しく調べてみると、史実における謎の深さと、キングダムでの創作の可能性の豊かさが見えてくる。中華統一という歴史的偉業に貢献した重要な将軍でありながら、その後の記録が完全に途絶えてしまうという現象は、歴史ロマンをかき立てずにはいられない。
史実の李信が残した三つの大きな謎は、現代の私たちにとって興味深い研究テーマとなっている。紀元前221年を最後に史書から姿を消すこと、秦末期の動乱に全く関与していないこと、そして趙高の大粛清から逃れた可能性があることは、それぞれ異なる歴史解釈を可能にしている。
キングダムにおける信の描かれ方では、原作者の原泰久氏が史実の制約を超えて、理想的な英雄像を創造している。「中華統一後もエピローグ的に描く」という発言からも、史実で途切れた李信のその後の人生が感動的に描かれる可能性が高い。
李信という人物の魅力は、その謎めいた最後にもある。完璧な記録が残る英雄よりも、謎に包まれた部分がある英雄の方が、人々の想像力をかき立てる。帰農説、粛清説、早期死亡説など、どの可能性にもそれぞれの説得力があり、どれが正解かは永遠に分からないかもしれない。
しかし、その謎があるからこそ、李信という人物は2000年以上経った現在でも、多くの人々の関心を集め続けている。史実の探求とフィクションの創作、どちらも李信という魅力的な人物があってこそ成り立つものである。これからも、この古代中国の英雄は、多くの人々の心を魅了し続けることだろう。
 ゼンシーア
ゼンシーア