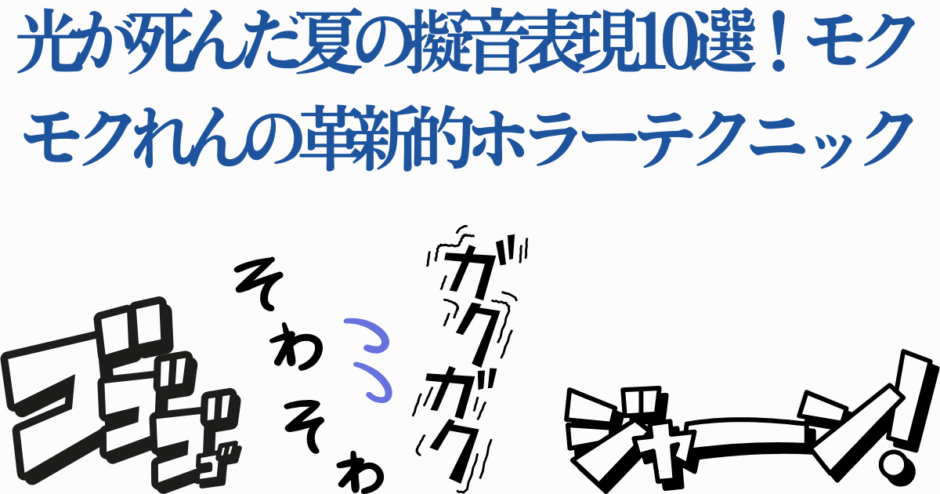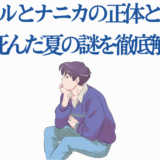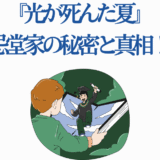本コンテンツはゼンシーアの基準に基づき制作していますが、本サイト経由で商品購入や会員登録を行った際には送客手数料を受領しています。
「シャワシャワシャワシャワ」——ただの擬音とは思えない不気味さと存在感。モクモクれん作「光が死んだ夏」が読者を魅了する最大の理由の一つが、この革新的な擬音表現です。「このマンガがすごい!2023」オトコ編1位を獲得し、累計300万部を突破したこの作品は、2025年夏のアニメ化も決定。従来のホラー漫画では補助的役割に過ぎなかった擬音を、物語の核心に据える独創的アプローチで新たな恐怖表現の地平を切り開きました。フォントの選択、文字サイズ、配置に至るまで緻密に計算された擬音は、見る恐怖から読む恐怖へと読者を誘います。本記事では、「光が死んだ夏」の魅力を擬音表現という切り口から徹底解剖します。
光が死んだ夏の擬音とは?

「光が死んだ夏」の世界に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのが独特の擬音表現です。一般的な漫画では手書きで表現されることの多い擬音が、本作ではフォントを用いて印字され、そのフォントの選び方、サイズ、配置に至るまで緻密に計算されています。特に「シャワシャワシャワシャワ」という蝉の鳴き声は、コマ枠を超えて描かれ、夏の風景に不穏な空気を漂わせる象徴的な存在となっています。この擬音表現は単なる効果音ではなく、物語の雰囲気を作り出す重要な要素であり、ホラー表現の新境地を切り開いたと言えるでしょう。
モクモクれんが描く独創的ホラー世界
モクモクれん氏による「光が死んだ夏」は、2021年8月31日より「ヤングエースUP」(KADOKAWA)にて連載が開始された作品で、作者の商業連載デビュー作です。三重県の山間部の集落を舞台に、幼馴染のよしきと光の物語が描かれていますが、山で行方不明になった後に帰ってきた光が別の「ナニカ」にすり替わっていることに気づいたよしきが、その「ヒカル」と呼ばれる存在と共に生活するという異質な設定が特徴です。
モクモクれん氏はホラー映画を「アトラクション感覚」で楽しむと語っており、「ゾワゾワするような感覚」を大切にした演出を心がけています。特に注目すべきは、擬音を含めた「ミスマッチさ」を重視した表現手法です。明るい夏という季節設定と不気味な物語内容のコントラスト、日常と非日常を分ける擬音の使い分けなど、読者の予想を裏切る展開とともに、独創的なホラー世界を構築しています。
「このマンガがすごい!2023」オトコ編1位の実力
2022年12月、「光が死んだ夏」は「このマンガがすごい!2023」オトコ編で1位に選出され、さらに「マンガ大賞2023」にもノミネートされました。この快挙の背景には、従来のホラー漫画の枠を超えた斬新な表現技法があります。
特に評価されたのは、オノマトペが霊的な存在として人の形を取って描かれるなど、擬音を単なる効果音としてではなく、物語の重要な要素として昇華させた点です。『ダ・ヴィンチ』編集長の川戸崇央氏は「見事な擬音」や「表情の演出」など、本作の読みどころの多さを指摘しています。
また、人外の存在となった「ヒカル」とよしきの間の複雑な感情が鮮明に描かれていることも高く評価されています。恐怖を感じる要素がさまざまに存在する中で、二人の関係性が物語の核心として描かれることで、単なるホラー作品を超えた深みを持つ作品として認められました。現在では累計300万部を突破する人気作品へと成長し、2025年夏にはついにアニメ化も決定しています。
光が死んだ夏で見られる衝撃的な擬音表現10選
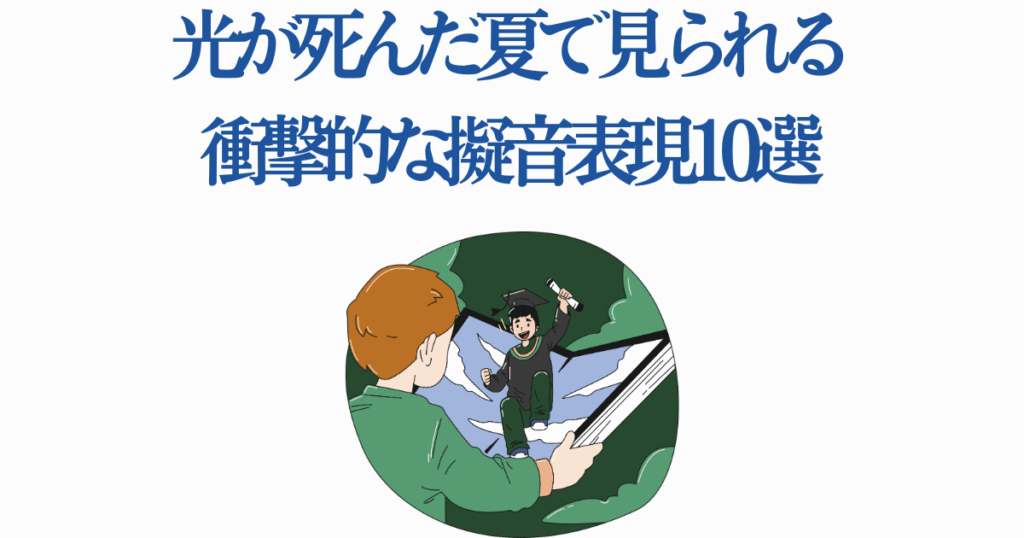
モクモクれん氏が生み出した「光が死んだ夏」は、従来の漫画表現の常識を覆す独創的な擬音表現で読者を魅了しています。手描きではなく活字フォントを用いることで生まれる違和感、文字の大きさや配置の工夫など、細部まで計算された表現技法が本作の大きな特徴です。ここでは、特に衝撃的な10の擬音表現を紹介し、その恐怖表現としての効果を解説します。これらの表現がアニメ化でどのように音響化されるのか、今から期待が高まります。
不気味さを演出する「シャワシャワ」の蝉の鳴き声
作品全編を通して最も象徴的なのが「シャワシャワシャワシャワ」という蝉の鳴き声です。一般的な「ミーンミーン」ではなく独特の表記を選ぶことで、読者に違和感を与えています。さらにこの擬音はコマ枠を超えて描かれ、まるで蝉の鳴き声が物語世界全体を包み込んでいるかのような印象を与えます。夏の風景と親和性の高い蝉の鳴き声が、本作では不穏な空気を醸し出す効果を生み出しており、日常と非日常の境界を曖昧にする役割を果たしています。
恐怖を増幅させる文字フォントの使い分け
モクモクれん氏は意図的に擬音を手描きではなく活字フォントで表現しています。これは「読んでもらいたい」という作者の意図によるもので、読者の目に入れたいところではフォント、意識しなくてもよいところを手描きと使い分けて表現しています。特に恐怖シーンではフォントの種類や太さを変えることで緊張感を高め、読者の心理に直接訴えかける効果を生み出しています。これは単なる視覚的な工夫ではなく、読者の「読む」という行為自体をホラー体験へと変換する革新的な手法です。
コマ枠を超える擬音表現のインパクト
「光が死んだ夏」では擬音がコマの枠を超えて描かれることがあります。これによって物語世界の境界が曖昧になり、まるで擬音そのものが実体を持って物語に介入しているかのような印象を与えます。特に「シャワシャワ」の蝉の声がページ全体に広がる表現は、読者の視線誘導と同時に、物語空間を拡張する効果をもたらします。アニメ化された際には、このようなコマ枠を超える表現がどのように映像化されるのか、大きな注目ポイントとなるでしょう。
恐怖シーンでの擬音の消失による異世界感
本作の特筆すべき点として、最も恐怖を感じるシーンではむしろ擬音が消失するという逆説的な演出があります。それまで大量にあった擬音が突然なくなることで、まるで音が消えた異世界に連れ込まれたような感覚を読者に与えます。この沈黙の演出は映画の音響効果にも通じるもので、視覚的な恐怖表現とあいまって読者の不安感を増幅させる効果があります。この手法は、漫画というビジュアルメディアの限界を超え、読者の想像力を最大限に活用したホラー表現です。
オノマトペが人型になる霊的表現
本作の最も革新的な表現は、第3巻15話で描かれるオノマトペが人の形をした霊的な存在として描かれるシーンでしょう。文字でありながら明確に人型を形成し、異様な速度で迫ってくる様子は、シュールでありながらも恐怖を感じさせる効果があります。擬音が単なる効果音ではなく、物語の中で実体を持った存在として描かれるという発想は、漫画表現の可能性を大きく広げるものです。この表現がアニメではどのように音と映像で表現されるのか、多くのファンが期待を寄せているポイントです。
怨念型の吹き出しと襲いかかる「く」
通常のセリフと区別するため、怨念や異形の存在が発するセリフには特殊な形状の吹き出しが使われています。さらに特徴的なのが、ひらがなの「く」が文字としての役割を超えて、キャラクターを襲うシーンです。文字自体が物語の中で実体を持ち、脅威として機能するという表現は、テキストとビジュアルの境界を曖昧にする革新的なアプローチです。文字が持つ形状そのものを恐怖の源泉として活用するこの手法は、モクモクれん氏の創造性を象徴しています。
日常と非日常を分ける擬音の使い分け
「光が死んだ夏」では日常シーンと非日常(恐怖)シーンで擬音の表現方法が明確に使い分けられています。日常シーンでは比較的整った配置と一貫性のあるフォントが使用される一方、非日常シーンでは不規則な配置や歪んだフォント、あるいは前述のように擬音の消失が効果的に用いられます。この対比によって、物語の進行に合わせた緊張感の高まりを読者に効果的に伝えています。アニメ化においても、この日常と非日常の音響的な対比が重要なポイントとなるでしょう。
文字サイズとアウトラインによる緊張感の演出
本作では文字サイズの大小やアウトラインの有無によって、音の大きさだけでなく空間の広がりや緊張感を表現しています。小さな文字で描かれた擬音は距離感や密やかさを、大きな文字は迫力や緊急性を伝えます。また、アウトラインの太さや色の使い分けによって、擬音自体に立体感や異質感を持たせることに成功しています。こうした細部へのこだわりが、読者の没入感を高め、より強烈なホラー体験を生み出しています。
読者の脳内で音を想起させる効果
モクモクれん氏は従来の「ガタン」「ドン」といった典型的な擬音ではなく、独自の擬音表現を多用することで、読者の脳内に新しい音のイメージを創出することに成功しています。これにより読者は既存の音の記憶に頼ることなく、作品世界に固有の音響体験を強いられ、より強い印象と恐怖感を感じることになります。漫画という無音のメディアでありながら、読者の脳内に鮮明な音を想起させるこの手法は、アニメ化に向けて音響監督にも大きな創造性を要求することでしょう。
擬音で表現される「ナニカ」の異形の恐怖
主人公のよしきが接する「ヒカル」の中に潜む「ナニカ」の存在は、直接的な描写だけでなく擬音表現によっても強調されています。人間の発する音とは明らかに異なる擬音を用いることで、「ナニカ」の異質性と恐怖を増幅させています。特に作中で「ナニカ」が現れるシーンでは、通常ありえないような擬音の組み合わせや配置が用いられ、読者に強い違和感と恐怖を与える効果があります。この「音」によって描かれる異形の存在は、アニメ化においてどのような音響効果で表現されるのか、多くのファンが注目しています。
光が死んだ夏と他ホラー作品の擬音表現比較

「光が死んだ夏」が革新的な作品として高く評価される理由の一つに、これまでのホラー漫画とは一線を画した擬音表現があります。従来のホラー漫画では視覚的な恐怖表現が中心でしたが、本作では擬音自体がホラー表現の核となっています。ここでは、伝統的なホラー漫画や伊藤潤二作品、そしてPOV(一人称視点)ホラーといった観点から、「光が死んだ夏」の擬音表現の独自性を掘り下げていきます。
伝統的ホラー漫画における擬音の使われ方
従来のホラー漫画では、擬音は主に情景描写を補助する役割を担ってきました。例えば「ガタン」「ドキドキ」「ザワザワ」といった定型的な擬音を用いて、恐怖シーンの雰囲気を盛り上げる手法が一般的でした。これらの擬音はいわば「ハンコ」的な役割を果たし、読者はそれを見ただけで「怖いシーン」であることを理解するよう条件付けられていました。
一方、「光が死んだ夏」では擬音そのものが恐怖の源泉となり、物語の重要な要素として機能しています。「シャワシャワ」という蝉の鳴き声は、通常であれば夏の風物詩として心地よいイメージを持つものですが、本作では不気味な存在感を放ち、読者に強い違和感と恐怖を与えます。このように日常的な音を不気味なものへと転換する手法は、従来のホラー漫画ではあまり見られなかった革新的なアプローチです。
伊藤潤二作品との擬音表現の違い
現代ホラー漫画の代表格である伊藤潤二作品と比較すると、擬音表現に対する姿勢の違いが鮮明になります。伊藤潤二作品では、独特の緻密で写実的な絵柄による視覚的恐怖表現が中心であり、擬音はむしろ抑制的に用いられる傾向があります。特に恐怖のクライマックスシーンでは、擬音を排して絵のみで恐怖を表現することも少なくありません。
対照的に「光が死んだ夏」では、擬音とビジュアルが互いに補完し合い、両者が一体となって恐怖を創出しています。伊藤潤二作品が「見せる恐怖」を追求するのに対し、本作は「読ませる恐怖」も同時に追求していると言えるでしょう。モクモクれん氏は擬音に至るまで徹底的にこだわり、読者の目に入れたいところではフォント、意識してほしくないところでは手描きというように使い分けています。この緻密な計算に基づいた擬音表現こそが、本作独自の恐怖体験を生み出す源泉となっています。
POV(一人称視点)ホラーを強調する擬音の効果
モクモクれん氏は、白石晃士監督のPOV(一人称視点)ホラー映画の熱心な鑑賞者であり、本作もPOV方式で描かれています。POVホラーの特徴は、主人公の視点と観客の視点を重ね合わせることで、恐怖体験を直接的に共有させる点にあります。「光が死んだ夏」では、擬音表現がこのPOV効果を強化する重要な役割を果たしています。
擬音を通して読者がよしきの聴覚体験を共有することで、まるで自分自身が物語世界に入り込んだかのような没入感が生まれます。特に恐怖シーンでの擬音の消失や、突然の大きな擬音の出現は、映画におけるサウンドデザインの手法を漫画に取り入れたもので、読者の心理的緊張感を高める効果があります。映画のサウンドトラックが観客の情緒に大きな影響を与えるように、本作の擬音表現は読者の恐怖体験を直接的に操作する力を持っています。
2025年夏のアニメ化では、これらの革新的な擬音表現がどのように音響化されるのかが大きな注目ポイントとなるでしょう。原作の緻密な擬音設計を活かした音響演出が実現すれば、新たなホラーアニメの表現領域を切り開く可能性を秘めています。
光が死んだ夏の擬音から見るホラー漫画の新潮流
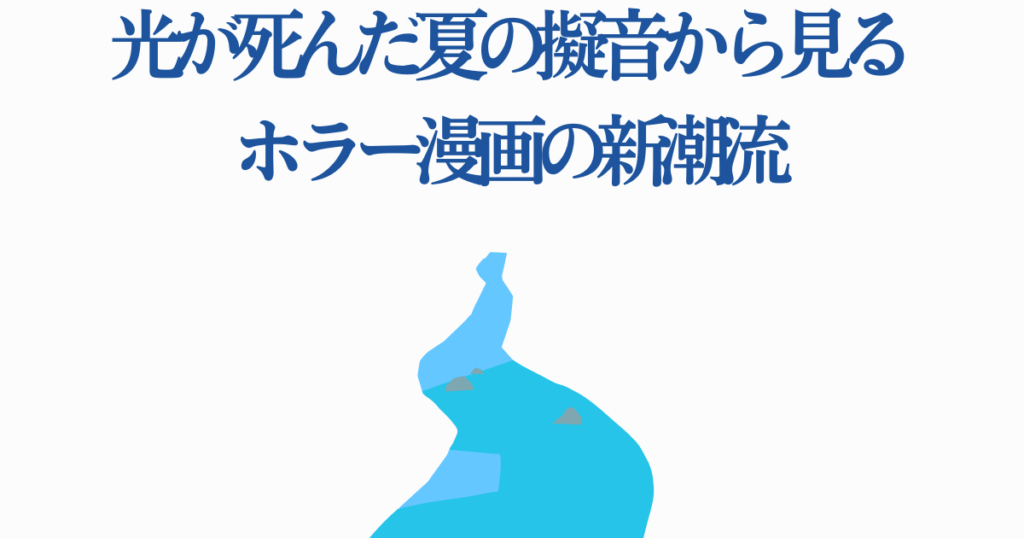
「光が死んだ夏」の登場は、ホラー漫画というジャンルに新たな風を吹き込みました。モクモクれん氏の斬新な擬音表現は、これまでのホラー漫画の常識を覆し、新世代のホラー表現として多くの読者の心を捉えています。本作が切り開いた新たな表現技法は、漫画におけるホラー表現の可能性を大きく広げ、今後の作品にも影響を与えていくことでしょう。ここでは、「光が死んだ夏」の擬音表現から見える、ホラー漫画の新潮流について考察します。
従来のJホラーとの表現の違い
「光が死んだ夏」以前の日本のホラー漫画、いわゆるJホラーは、主に「呪い」「怨念」「都市伝説」などの日本特有の恐怖要素を題材にしたものが主流でした。視覚的な恐怖表現が中心で、歪んだ顔や異形の存在、血や暴力的な描写などを通じて読者に恐怖を与える手法が一般的でした。
一方、「光が死んだ夏」では三重県の山間部という現実的な舞台を選びながらも、擬音という聴覚的要素を視覚化することで新たな恐怖表現を生み出しています。モクモクれん氏は自身がホラー映画を「アトラクション感覚」で楽しむと語っており、「ゾワゾワするような感覚」を大切にした演出を心がけています。これは従来のJホラーのような直接的な恐怖よりも、微妙な違和感や不穏さを通じて読者の想像力を刺激する手法です。
さらに本作では「ミスマッチさ」を意識的に取り入れることで、より深い恐怖感を創出しています。明るい夏という季節設定と暗い物語内容のコントラスト、親友のような存在が異質なものに変わるという設定など、日常と非日常の境界を曖昧にすることで読者の心理的安定を揺るがしています。この手法は、あからさまな恐怖描写に依存せずとも、読者の心に深く入り込む効果を生み出しています。
擬音重視の新世代ホラー作品の台頭
「光が死んだ夏」の成功により、擬音やテキストを重視した新しいタイプのホラー漫画が注目を集めるようになりました。これまでの視覚中心のホラー表現から、テキストや擬音という要素が新たな恐怖表現のツールとして認識されるようになったのです。
この新潮流の特徴は、漫画というメディアの持つ「音のない表現」という制約を逆手に取り、読者の想像力を最大限に活用する点にあります。実際の音を聞くよりも、脳内で想像させる「音」の方が、時に強烈な恐怖を生み出すことがあります。モクモクれん氏は擬音の「読ませる」という部分に着目し、フォントや配置を徹底的に計算することで、読者の脳内に鮮明な音のイメージを創出することに成功しています。
この成功に影響を受け、従来のビジュアル重視のホラー漫画に加えて、テキストや音の表現に重きを置いた作品が増えつつあります。「音」という見えない恐怖を可視化し、読者の想像力を刺激するという手法は、今後のホラー漫画の表現領域をさらに拡大していくでしょう。2025年夏のアニメ化を経て、この新潮流はさらに広がっていくことが予想されます。
SNSで話題を呼ぶビジュアル表現の重要性
「光が死んだ夏」は当初、モクモクれん氏がX上で公開したことがきっかけで大きな反響を得ました。その後TikTokでも話題となり、特に女性読者から高い支持を集めたことは、SNS時代における漫画のあり方を示す重要な事例です。本作の成功要因の一つに、SNSでシェアしたくなるようなインパクトのあるビジュアル表現があります。
特に本作の擬音表現は、単に読むだけではなく「見せる」効果も高いものです。「シャワシャワ」という独特の蝉の鳴き声や、怨念型の吹き出し、人型になるオノマトペなど、一目で「これは何だろう?」と興味を引くビジュアル要素が満載です。SNS上でこれらの画像が共有されると、作品自体を知らない人でも強い印象を受け、興味を持つきっかけとなります。
現代のホラー漫画は、単に怖いだけでなく「シェアしたくなる怖さ」という新たな要素が重要になっています。「光が死んだ夏」は、読者の「これは何だろう?」という好奇心を刺激し、「他の人にも見せたい」という共有欲求を満たす絶妙なビジュアル表現を持っています。特に擬音表現は、その独自性と視覚的インパクトから、SNS上での拡散力が非常に高い要素となっています。2025年のアニメ化に向けて、これらの要素がさらに注目を集めることは間違いないでしょう。
既刊6巻から見る擬音表現の進化
「光が死んだ夏」は現在第6巻まで刊行されており、巻を追うごとにモクモクれん氏の擬音表現はさらに洗練され、進化を遂げています。初期の頃から特徴的だった「シャワシャワ」の蝉の鳴き声は、物語の進行とともにその意味合いや表現方法に変化が見られ、読者の恐怖体験をより深いものへと導いています。
特に注目すべきは第3巻に収録された15話で描かれる、オノマトペが人型になる霊的表現です。これは擬音表現の可能性を大きく広げる革新的な試みであり、モクモクれん氏の創造性が最も発揮された瞬間と言えるでしょう。この表現は多くの読者に強い印象を与え、作品の魅力をさらに高める要素となりました。
また、物語が進むにつれて「ヒカル」の異質性や「ナニカ」の正体に関する描写が深まるのに合わせ、擬音表現もより複雑で多層的なものへと変化しています。初期のシンプルな不気味さから、より象徴的で意味深い表現へと進化していく様子は、モクモクれん氏の作家としての成長を物語るものです。
2024年12月時点で電子版含めシリーズ累計300万部を突破したこの作品は、今後も擬音表現を中心とした革新的なホラー漫画として、さらなる進化を遂げていくことでしょう。2025年夏のアニメ化に向けて、最新巻ではどのような表現が見られるのか、多くのファンが期待を寄せています。
光が死んだ夏の擬音表現10選まとめ
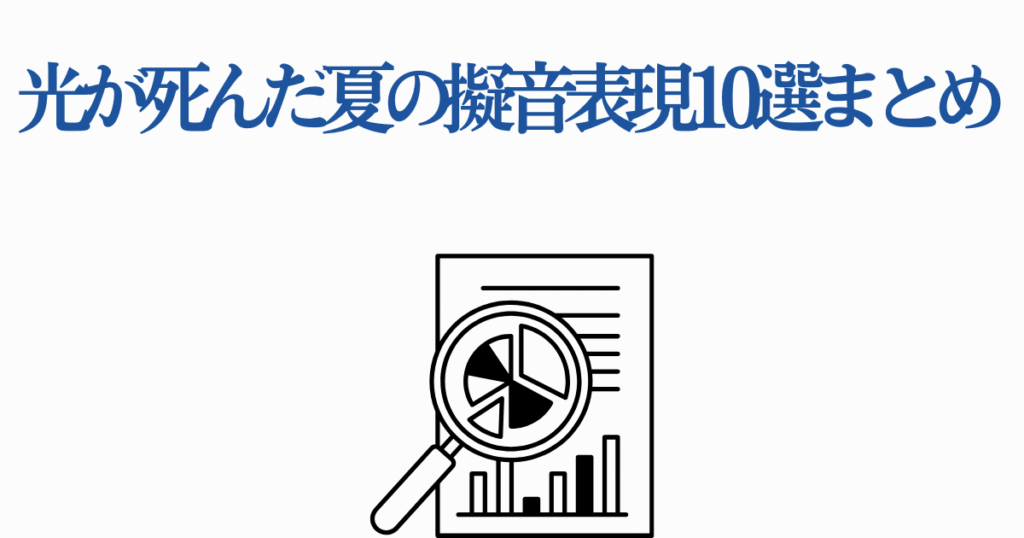
モクモクれん氏が生み出した「光が死んだ夏」は、従来のホラー漫画の概念を覆す革新的な擬音表現によって、多くの読者を魅了してきました。本記事で紹介した10の特徴的な擬音表現は、この作品の魅力を深く理解する上で欠かせない要素です。特に「シャワシャワ」という蝉の鳴き声は作品全体を象徴する存在として、夏の風景に不穏な空気を漂わせています。また、フォントの使い分けや文字サイズ、配置による緊張感の演出、コマ枠を超える表現、恐怖シーンでの擬音の消失など、細部にわたる緻密な計算が「光が死んだ夏」独自の世界観を作り上げています。
さらに、オノマトペが人型になる霊的表現や、怨念型の吹き出しと襲いかかる「く」の表現など、従来の漫画表現の常識を超えた手法は、テキストとビジュアルの境界を曖昧にする革新的なアプローチとして高く評価されています。モクモクれん氏の擬音表現に対するこだわりは、単なる効果音としてではなく、物語を構成する重要な要素として機能しており、読者に強烈な印象と恐怖体験を提供しています。
2025年夏に控えたアニメ化では、これらの独創的な擬音表現がどのように音響化されるのかが最大の注目ポイントとなるでしょう。竹下良平監督とCygamesPicturesによる映像化で、原作の革新的な表現がどのように再現されるのか、ファンの期待は高まるばかりです。「光が死んだ夏」が切り開いた新たなホラー表現の可能性は、今後の漫画・アニメ業界にも大きな影響を与えていくことでしょう。「このマンガがすごい!2023」オトコ編1位、累計300万部突破という実績からも、モクモクれん氏の革新的な擬音表現がいかに多くの読者の心を捉えたかがわかります。アニメ放送開始までに原作を読み、その独創的な擬音表現の魅力を体験してみてはいかがでしょうか。
 ゼンシーア
ゼンシーア